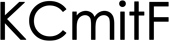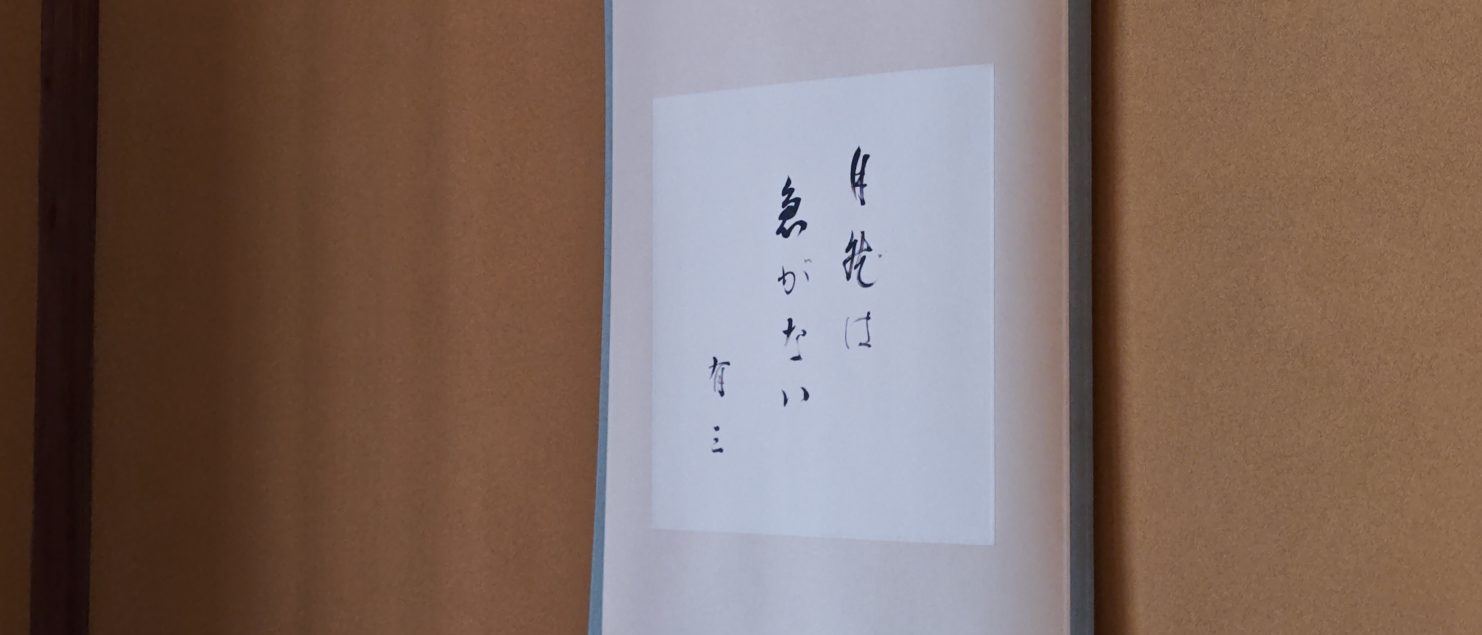なぜ今こそ日本のものづくりを、私たち日本人が見つめるべきなのか?—2025年頭所感
旧暦の新年を迎えて、2025年の年頭所感的なものをここに記しておきたいと思います。主に自分自身に向けたメッセージ、宣言とも言えるのですが、日本のものづくりの将来を担っている方々にとっても何かしら示唆になるのではないかと思い、公開し態度表明とする次第です。
さて、2024年はコロナ禍を過去とし本格的にコロナ後の時代に突入した最初の年として認識しています。象徴的なところでは夏のパリでのオリンピックがありました。2021年に開催されたコロナ禍の東京オリンピックから新しい時代を彷彿させるスポーツの祝祭が、人類を襲った未曾有のパンデミックを乗り越えたと印象付けるイベントだったように思います。
一方で、私達の様々な活動はコロナ以前のようになりましたが、グローバル化した現代においては日本とは遠い場所で起こっている戦争や紛争は他人事ではなく、人道的な部分だけで無くエネルギーをはじめとする資源や、輸送のコストなどに反映され、私たちの暮らしにも大きく影響する事を実感した年だったとも言えます。欧米ではコロナ禍の財政出動の反動もあり、いち早く光熱費や物価高が発生していましたが、日本にも物価高の流れがやってきました。この影響は人口減少が避けられない2025年以降も続くでしょうし、それを見据えたビジネスでの対応が求められてくると思います。
生活にかかるコストの上昇、世界の情勢が不安定なことによる先行きの見えない不安感はいつでも人の消費マインドを引き下げます。こうなってくると輸出入品のように輸送という付加コストがかかる製品には少し不利な状況になっている事は想像に難くないと思います。
しかし、日本は現在円安という局面を迎え、あらゆる通貨に対して円が弱い状況が続いています。この為替の状況がいつどうなるのかは誰にも予測がつかない事でありますが、前段で触れた消費マインドが本来的には下がっている状況では、特にインバウンド観光客に「自分の国で買う輸入されたものより日本で買ったら安い」とか、「今円が安いうちに買っておくのが得だ」というバイアスがかかっている状況は認識しておいた方が良いと思います。このコントロール不能な前提条件が変われば、吹き飛ぶ需要とも言えるからです。インバウンド観光関連消費は購買は国内で行われているので見えにくいですが、海外での売上に近いような汽水域の様な売上です。この数字を見誤るとターゲットという観点でマーケティング戦略や事業戦略を間違えることになるので、注意が必要です。
では日本の内部の状況は今どうなっているのでしょうか?私が経営してる小さな日用生活品の小売店「Supermamam mit tobuhi」ではコロナ禍の前までは、伝統的工芸品のような高付加価値商品は
1. その価値を理解して買う事が出来る人
2. 理解してもなかなか手がでない人
3. あまり興味が持てない人
と大きく分けると三つのセグメントがありました。興味深かったのはコロナ禍で外出制限がかかり、生活空間で過ごす時間が必然的に増えた時に「2→1」と変化する人が増えた事です。当時来店客数はどんどん減り、営業自粛要請の適用外だった生活用品店はどうしたものか?と悩んでいたのですが、不思議と売上が大きく落ち込む事は無く、むしろ月によっては前年より伸びたりもしました。また、マスクや医療機器が不足する状況で我々の暮らしの為の商品がいかに世界のサプライチェーンに依存しているかが浮き彫りになった結果、「日本でつくる事」の重要性を感じた方が老若男女増えたことも実感しました。これは日本だけで無く、世界中で発生していたのではないかと思います。事実、海外で自国のものづくりを見つめ直すトレンドは今も続いています。
しかし、昨年は為替による物価高や、社会コストは上昇するが実質賃金は伸び悩むような経済状況で、日用生活品の売上は全国的には下がっていたのでは無いでしょうか?私の店ではシーズンギフトの需要が減ったり、自分へのご褒美的な消費がコロナ前に比べると大分少なくなったなと実感しています。コロナ禍で価値を理解する人や、日本のものづくりを応援したい人が背景では増えた中でちょっと残念な現在の景気感だと思います。
そういう状況もあって2024年は私にとっては悩みの多い年でも有りました。2012年にKCmitFを立ち上げた際は、「日本のものづくりは世界からまだまだ必要とされている」と掲げ、日本各地の伝統的工芸品の海外販路拡大に邁進し、突き詰めれば突き詰めるほど成果も出やすい環境でした。単純に「価値」が伝わっていない、存在を知らない市場でそれを伝えていけば行くほどビジネスは広がっていく時代だったとも言えます。現在はこちらから情報をセレクトしてPushしなくても、Webを通じて簡単に情報収集が出来るので、基本的な情報発信と、コンタクトに対しての受け答えが出来れば、興味を持たれた商品については取引をしたい側からアプローチが来る時代です。なので独自の情報発信とコミュニケーションを含めた対応力が以前より重要度を増しています。
そういった時代に対して私達がとった一つのアプローチとして、lo-opを通じたプロジェクトkyojiが挙げられます。kyojiはものづくり事業者間でコンソーシアムを形成し、共同で海外展開等のテーマに取り組むプロジェクトなのですが、「メイドインジャパンを再定義する」という言葉を掲げ、これからの日本のものづくり産業のあり方を生産事業者が連携することで模索し、共に成長し向上する為に活動を共にしています。今年で8年目を迎えるプロジェクトですが、2024年からは海外展開だけで無く、国内市場においても力を合わせるという方針が生まれ、今年はその成果として面白いアウトプットを披露する準備が進んでいます。この様に日本から新価値提案が生まれていけば、そこからやがてまた海外への道も新しい形で拓けていくと思います。
KCmitFとしても国内に対しても、海外に対しても自分が提供できる事業サービスそのものをUpdateしていくタイミングがきている事は数年前から自覚していました。時を同じくして仕事としての幅も、商品開発や海外展開支援中心だったものが、地域の産業の将来戦略を一緒に考える事だったり、自治体に入り込んで地域政策の実行のお手伝いや策定の為の提言をする事にも携わるようになってきておりました。国内にはものづくりを支えるミュニティの高齢化、制度や仕組みの停滞など人口減少社会へ向かうベクトルに起因する共通背景があります。なので職人や事業者を単体で支援する事はもちろん、その産業を支えるコミュニティや行政機能に対しても今までとは異なる働きかけが必要だと日々現場で実感しています。
しかし、状況や業務の内容が変化したとしても、私自信が共に生きたいと願う「ものづくり」という軸は変わりません。それどころか、前述の様な大きなテーマに向き合えば向き合うほど、日本のものづくりの文化や精神がこれからの日本の為の様々な策を打ち出す為のポテンシャルを秘めていると考える様になりました。それ故に、日本のものづくりの未来とはどうあるべきなのか?というテーマにずっと向き合いながら、自分がミッションとすべき事を整理する為に四苦八苦していたのです。幸いなことに、一度お仕事をご一緒せて頂くと長期に渡り業務を継続する機会と相手に恵まれたこともあり、短期では無く長期で価値を生み出す事にこれまでずっと集中出来たからこそ、産みの苦しみの時間を経験出来たと今では思っています。
2025年からKCmitFを中心として集中して展開していく事業テーマを大きく括ると、下記の様に3つになります。
1. 国内市場への啓発(BtoC、BtoB)
2. 長期戦略としての海外販路開拓&事業開発支援(いまの事業テーマ)
3. ものづくり産業支援側の支援(行政機関)
簡単にアクションとして列記すると、(1)は小売店でのものづくりを学ぶ一般の方向けの勉強会の開催、また自社以外の同業小売店の販売力を高め、つくり手側とのこの時代におけるWin-winを再構築するアクションをこれまでの経験にもとづいて広げていきます。加えて、KCmitFのメディア的機能を大きく強化し、ものづくりやその精神に関しての情報発信や、携わる事例にまつわるエピソード、思考のプロセスの発信をテキストベースで、今の記録や、視点の共有の為に動画コンテンツの制作と発信をしていきます。
(2)はこれまでやって来ていることの継続となりますが、商品開発や海外での販路開拓、事業戦略設計支援、企業顧問的な既存支援の部分は勿論継続するとして、事業の経営に携わっている方や将来その職に就く方へ対して、研修の様な形で経験値を上げていただいたり、気づきを得られる様な事業を展開して行きたいと思っています。ものづくりは「人」です。故に、これからのものづくりを支える人が、変化し、成長していく事が日本のものづくりの未来に直結しているのです。
(3)はこの12年の活動を経て、現在1番重要だと思っているアクションです。産業としてのものづくりは、職人や事業者が単独でやるものでもなく、様々な役割をもった人達がそれぞれの役割を果たし、連携する事で成り立つものです。その役割分担の工夫には地域性や国民性が宿っています。そしてこれを支えるのが地域コミニティであり、逆もまたしかりで地域コミュニティを支えるのが産業でもあります。地域コミュニティの運営機関は行政などの公的機関ですが、ここがしっかりヴィジョンを持ち機能しないと、地域コミュニティ自体が衰退していくことになります。行政機関はともするとどこか別の地域のベストプラクティスや中央からの情報でアクションを設定しがちですが、そもそも地域ごとに特性が異なる中でスムーズにそれらがインストール出来ない、機能しないというケースも沢山見て来ました。一方で働き方改革等で行政職員の業務はオーバーフローしがちな状況があり、理想的な活動もなかなか出来ないジレンマに対して、私がこれまで培った地域に入り込んでの戦略設計の経験を元に、お手伝い出来る事があると思っております。
地域に根付く価値観や歴史をベースに、訪れる未来と現在の状況を鑑みて将来の為の施策を決定する。その為の支援を外部の専門家として行うことで、結果的に日本のものづくりを未来に繋げる事が出来ますし、またこの価値をより多くの外側のコミュニティに伝えていく機会を生み出せると思っています。これらを蓄積し束ねていく事で、将来的にはしっかりとした国策提言にも繋がっていくと考えています。
本当に長くなりましたが、個別のテーマや詳細に関しては今後またお伝えする様にしていきます。
「ものづくりを通じて、日本らしい幸せのあり方を追求する」という言葉を数年前から掲げているのですが、これは日本の人達が自分たちの幸せを考えたとき、また次世代の為に考えたときに、ものづくりの周辺にはそのヒントが沢山存在している事を伝えて行きたいなと思って考えた言葉になります。まずはそこに目を向けてみる事で気づきが生まれ、一人一人が考え方や意識を自分達の未来に向けていく事が出来れば、「与えられた定義では無い、私たちの幸せ」を掴めるのでは無いか?と考えます。
それはまた来る人口減少社会を日本人らしくポジティブに迎え、そのスタイルがまた世界の人達に「日本人はそうしたのか!」と伝わっていけば、同じテーマを迎える際の示唆にもなるのでは無いか?より深く日本が理解されるのではないか?と思っています。現在の経済指標ではちょっと元気のない私達の日本ですが、未来においては別の指標で先進国になっている。そんな事は、私たちがしっかり日本のものづくりを見直した先には普通に起こせると思っています。
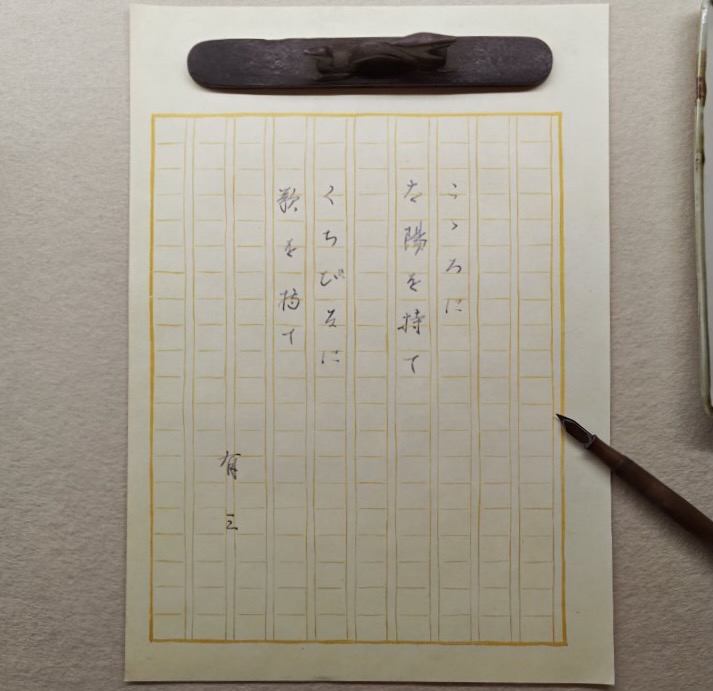
KCmitF 大谷啓介