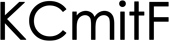デザインに課したミッション 〜 it’s beyond the design
2025年6月、シンガポールのSupermamaは東京で開催されたインテリア ライフスタイル展にて、“weareSuper”という新しいコレクションを世界に先駆けて発表しました。私ももうかれこれ10年以上彼等と一緒に仕事をし、その歩みを少なからずすぐ側で見てきていますが、節目節目でSupermamaは新しいチャレンジをスタートし、自分たちの活動のフィールドをより強固なものにしてきました。今回もその節目の一つにあたるのかなと思います。
さて、冒頭で紹介した“weareSuper”は、ディスエイブルのアーティストのアートワークをコアに、Supermamaのデザインチームがプロダクトデザインの観点で監修し、アーティストとデザイナーの協業によって完成させた、有りそうで無かったブランドと私は解釈しています。日本でも障害を持った方の作品、アートワークの市場流通を図り、アーティストの経済的な自立や、支援団体の活動補助、社会的認知の向上を図る動きはあちこちに存在しますし、またそれをマーチャンダイズや公共に繋げ、さらに経済活動や広報効果を高める仕組みも注目されています。ともすると、似たような、同じような、と評価されてしまうかもしれないweareSuperのアプローチですが、インハウスのデザイナーが深くコラボレーションするという部分にSupermamaの独自性が強く現れていると、今回展示会での発表に立ち会いながら思った次第です。。

一般的にディスエイブルの方々のアートワークは、福祉の観点で強く見られがちだったり、アートに対するリスペクトからオリジナルの形態によってはマーチャンダイズがし難いものがあったりする為、経済的自立を目的とすると商用化に向いたものと向いていないものとに作品が分かれてしまう一面があると思います。しかし作品によってはアーティストの感性や、表現の個性、テーマの設定など、私たちの常識を揺さぶるような、鑑賞者へ感情的に、直接的に訴えてくる強さを備えているのも魅力の一つです。
weareSuperのアプローチは、その魅力をどのように幅広く市場へ接続し、経済も含めたインクルーシブな環境を真の意味で構築するかに有ります。アーティストと作品の本質にデザイナーが向き合いながら、プロダクトに合わせたエディティングをデザインという形で実現していきます。ほぼオリジナルのアートワークのままにデザインされている商品もあれば、オリジナル作品のメタファーのような、新たな作品/デザインに昇華しているものもあります。
東京でのコレクションの発表の際に、Supermamaのデザインチームの中心であるプリシラに聞いたところ、実際の対話の作業には非常に大きなエネルギーと時間を費やすことになるけど、アーティストやその支援者と自分達がお互いに納得出来る様に丁寧にコミュニケーションを図りながら、最終的なプロダクトデザインに落とし込まれるそうです。またアーティストも、自身のクリエイティブが他のクリエーターとの対話を通じて新たな作品へと変化していくプロセスや、自身では想像もしていなかったプロダクトが誕生することが、新しい刺激にもなっているそうです。素敵なケミストリーですよね。

これを聞いた時に、一般流通する最終商品を購入するユーザーから、流通とマーチャンダイジングを図るSupermamaと、アートワークを生み出すアーティスト、その支援者の全てがベネフィットを得られる仕組みになっているビジネスデザインも秀逸だなと感じました。ユーザーは新しい感性の商品を手にすることができ、Supermamaはそのプロデュース力とビジネス力で収益を得て、アーティストも販売収益を手にすることが出来るし、支援者も結果負担が軽減されます。このエコシステムが構築できて初めて、インクルーシブな社会が実現できる。それがSupermamaがweareSuperに宿したミッションだと思っています。
Supermamaの創業者であるEdwinがこの事業のプランニングを始めたのは何年も前に遡るのですが、私も度々このアイデアに関しての話を聞き、関係者への説明を図ったり、時には一緒にリサーチをした事もありました。ぼんやりと自分なりに解釈していたところから、ようやく今回プリシラから話を聞いて、真剣にインクルーシブな社会実現にデザインの力で貢献する、それがSupermamaのこれまでの実績と経験に基づいた、実現性を持った社会的なミッションであると理解できました。
長年、デザインプロデュースをしたオリジナル商品(売れるものも、売れないものもある)を自分たちで売り続けてきたSupermamaだからこそ出来るアプローチで、同じスキームをそれぞれの専門家で構築しても、積算コストが最終販売価格に反映された結果、期待通りの数量を販売するのは難しいだろうと思います。アートワークありきになりがちな商品開発に対し、実売の観点から最適なフォーマットとしてのプロダクトをセレクトし、そのフォーマットに最適化させる為のデザインには勿論生産効率の観点も含まれています。売れなくては意味を成さない取り組みに正面から対峙し、売れる様にデザインプロデュースしていくのは簡単ではないはずです。

またこのSupermamaの取り組みに賛同し、最初のコレクションの大部分で開発・製造を担当したのも長年の取組先として知られる有田のキハラでした。Supermamaとキハラの出会いの物語は前述(※過去記事リンク)に有りますが、そこから始まった関係性も今では10数年以上に渡り、この長い時間の中で開発・試作した商品数も膨大な量になります。この技術的な挑戦や積み上げた経験値が今回のweareSuperのデザインプロデュースに活きていることは言うまでもありません。品質や代案提案力等を通じ長年に渡る信頼関係が育まれ、それに伴って産地や磁器製品に対しての知見も深まり、その結果、製造者としてのポテンシャルを見込まれて重要な新ブランドのローンチコレクションの製造を託されたと思います。

新しいコレクションの発表という瞬間を切り出すと、華やかな新しい側面、自由で創造的な面が目立ちますが、この瞬間へ辿り着く経緯は過去の試行錯誤や、継続による積み重ね、思考時間に比例した知見、お互いの信頼等があってこそ成り立っています。私自身も東京で店舗を経営しており、日々ユーザーの方々と接客販売をしていますが、今の時代はとにかくモノをコロナ禍前の様に売るのは難しくなったと感じています。我々がメインで取り扱う生活の道具は、これまでも機能性、デザイン、コストパフォーマンス等、色々と時代の流れの中で訴求ポイントが変化してきましたが、今はまたその転換を迎えていると感じます。モノはもはやモノ(機能やデザイン的優位性の軸)で購買されるのではなく、それが単なるモノ以上と認知される部分の存在や、それがあったとしてもそれがユーザーに伝わる環境で販売出来ているか?で売れる時代なのではないかと思っています。
まだ適切に言語化できていないのを承知で粗く述べるとすれば、左脳的にリーチするプロモーションではなく、右脳的に反応するエモーションがあるかないかが問われているとでも言いましょうか。またエモーションも言っても“衝動”の様なことよりも、“感嘆”のような深い関心、興味、願いなどを含む知的揺さぶりのようなものというニュアンスです。エモーションが強ければ濃いニッチ層向けになり、多少の高額でも売れる商品になります。一方で広く共感されるようなエモーションであれば、幅広く売れるが価格が重要なファクターになっていく様な商品になります。

こういった市場環境の中でweareSuperの取り組みは、アート×デザインでソーシャルシフトにチャレンジするという非常に強いエモーションがあり、それは国境や世代を越えていくテーマでも有ります。これまでシンガポール中心に築き上げられた彼等のブランド力を、weareSuperはさらにボーダレスに広げてアプローチ出来る、そんなポテンシャルを持ったブランドの誕生を、展示会場で来場者へ説明をしながら、その反応を伺いながら強く感じました。
正式な流通開始は2025年中ということで、現在も商品開発・生産は継続していますが、それをどのような形で伝えていくのか、どんな仕掛けを用意していくのか?新しいSupermamaの取り組み、weareSuperに是非注目して頂きたいと思います。
※Supermamaの取り組み、キハラの取り組みをもっと知りたい!という方はお気軽にお問い合わせください。